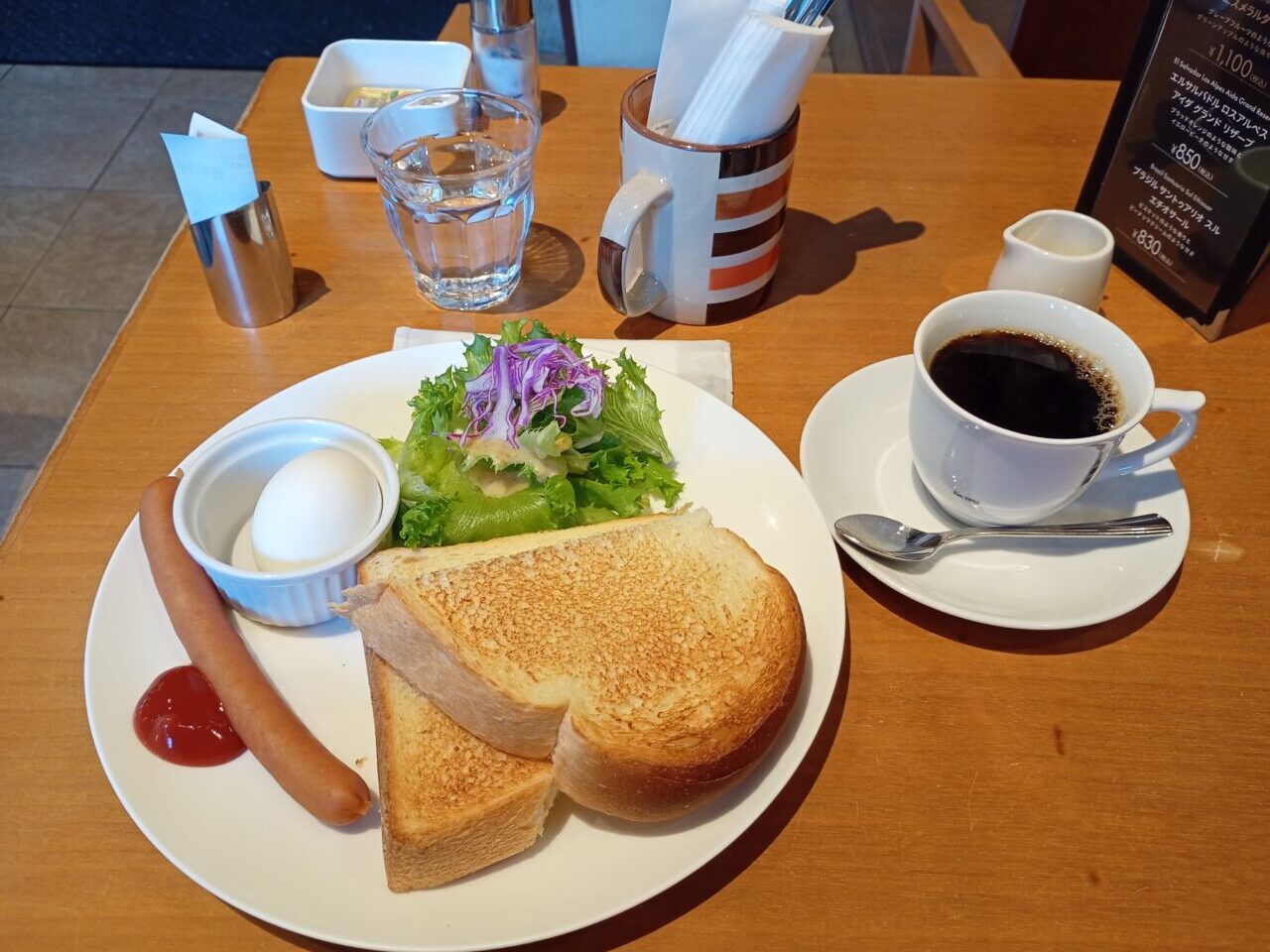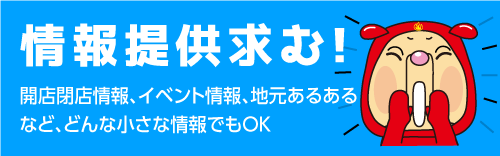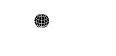【京都市西京区】かつて京に一番近い宿場町として栄えた樫原の本陣跡を見せていただきました!
国道9号線千代原口から物集女街道沿いに下がっていくと、樫原という京都市の「界わい景観整備地区」に至ります。交通量も多い道路から少し西に入ると一転、昔ながらの町家が続く風情ある風景が広がっています。2025年1月30日に縁あって「樫原本陣」を見せていただくことができました。

樫原宿は、古くから交通の要所とされ、江戸時代には山陰道の一番都寄りの宿場町として、参勤交代などで栄えました。「樫原本陣」は、江戸時代に参勤交代で往来した大名たちが宿舎とした陣屋遺構です。京都市内では唯一残る本陣遺構で、平成4年に京都市指定有形文化財として登録されています。「本陣」とは、大名・公家などの限られた人々だけが利用できる宿泊施設のことです。

玄関を入ると、昔ながらの土間から続く段差があって、上がると奥の主屋へと繋がっています。南側の「三の間」から「二の間」、そして西列最奥の6畳は床を一段上げて「上段の間」として造られ、まさに「書院造り」の構成となっていて、本陣座敷としての様式を整えています。

樫原本陣跡保存会の玉村隆史代表理事によると、上段の間には高松藩の松平家を始め、由緒ある大名家のお殿様が座し、手前の部屋は忍びのいる武者隠しの間だそうです。この本陣は側近の20人ほどが利用し、まわりの脇本陣にお供の人たちが宿泊したのだとか。桂川が氾濫した際には、500人の人たちが足止めをくらったといいます。

参勤交代のために1年前から予約し、出立すると現在の樫原の交差点を下がって、伏見を抜け、江戸へと向かったのでした。残念ながら、寛政9年(1797年)の大晦日に類焼したため、現在の主屋は寛政12年(1800年)に再建されたときのものです。内部の一部には大きく手が加えられていますが、西面・正面寄りの各室は改造が少ないそうです。

主屋の後方にある土蔵だけは焼け残り、棟札により明和3年(1766年)に建てられたものであることが判明しています。気楽に見学してほしいと遊び心で、お殿様変身グッズも置いてあって、これには外国人の人たちも大喜びだそうです。歴史ある趣きを今に伝える旧山陰街道の宿場町に立ち寄ってみてください。
「樫原本陣」はこちら↓