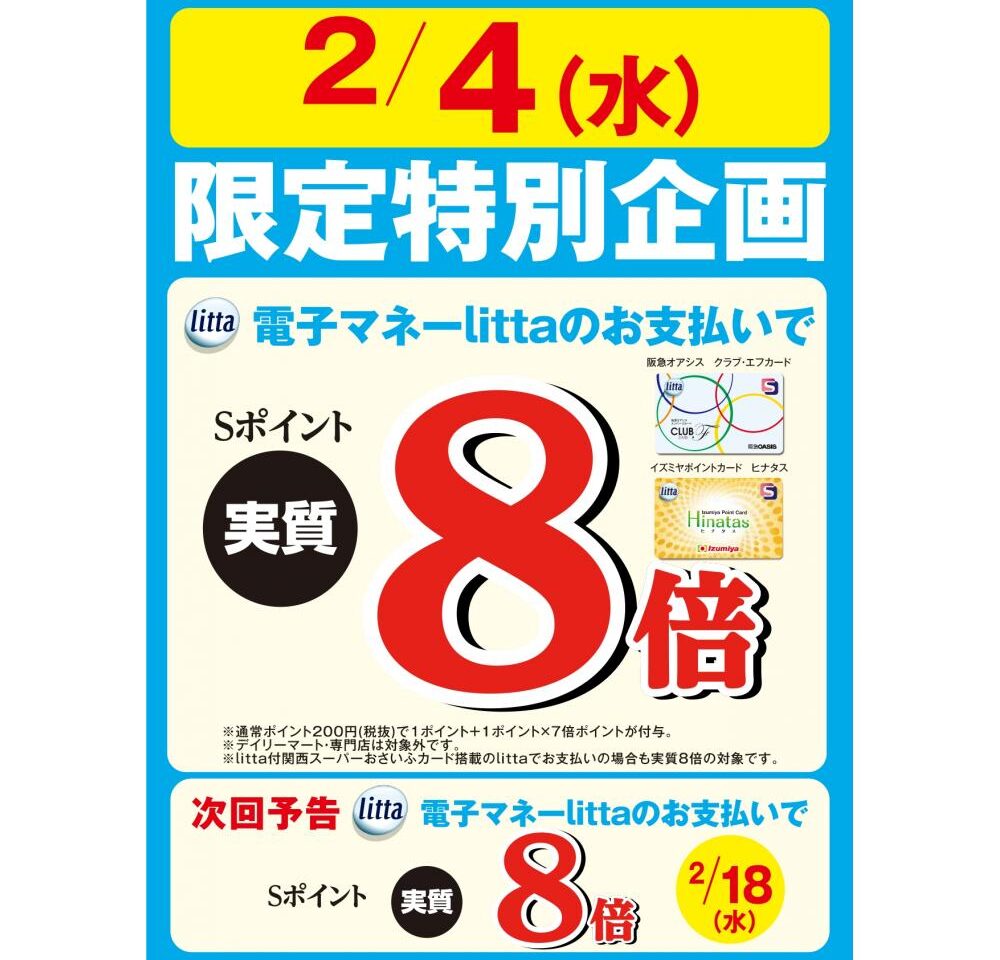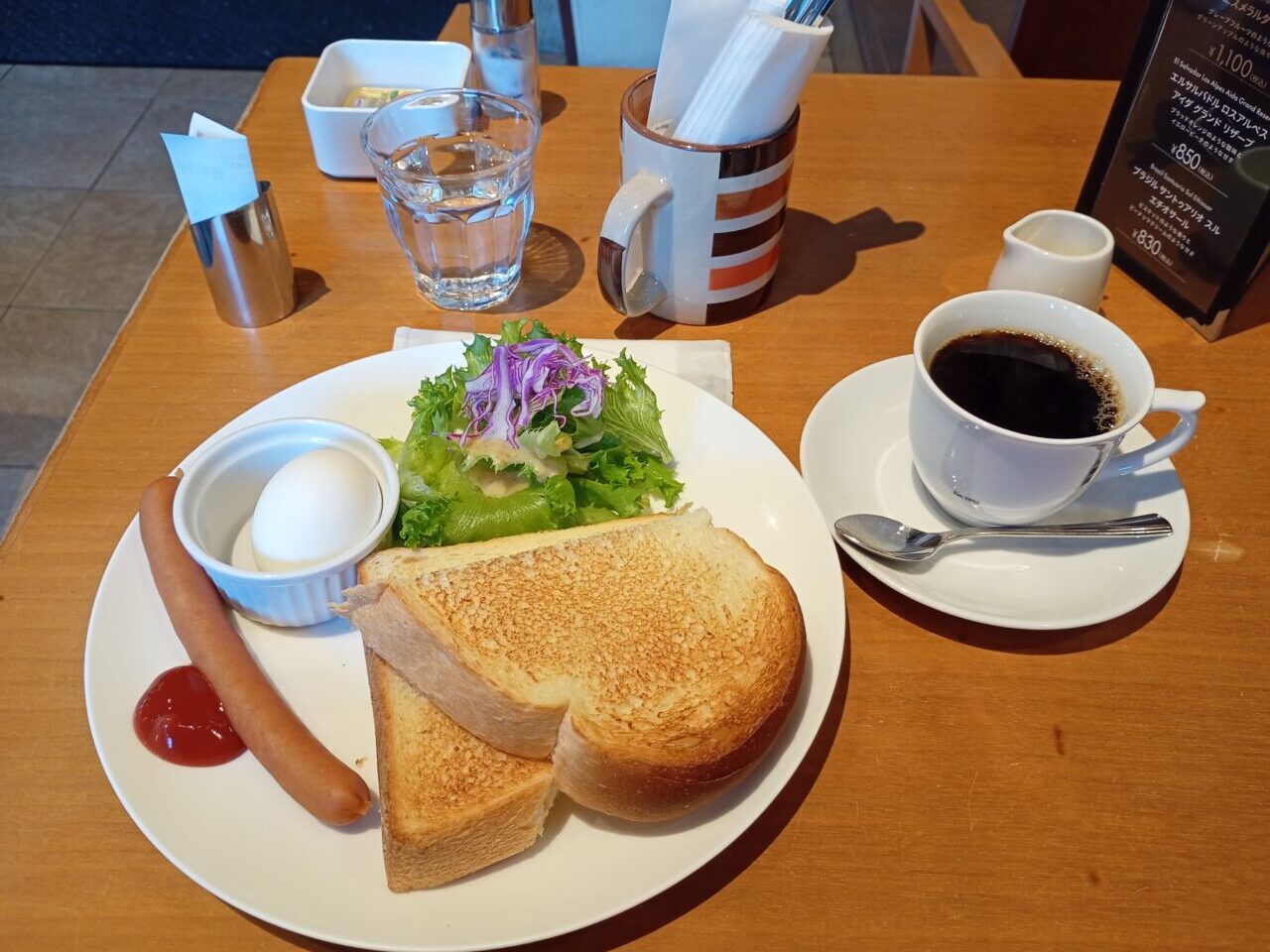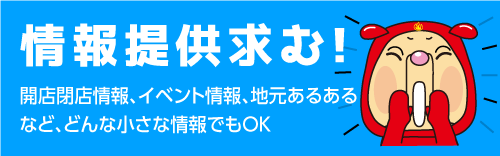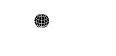【京都市上京区】今が見ごろ、1200年続く閻魔様の寺で普賢象桜が満開 庵主様に聞きました!
京の北の基点、陰陽道に基づく玄武の山とされる船岡山の北西はかつて「蓮台野」と呼ばれ、葬送の地でした。その現世と冥界の境目ともいわれる地に、かの小野篁卿によって建立されたと伝承されるのが「千本ゑんま堂」です。フゲンゾウ桜やショウゲツ始め、八重に咲く独特の重厚感のある遅咲きの桜が咲き誇る境内へ、2025年4月18日に訪れました。

ここに来たら、まずは本堂に安置されている、冥界の裁判官といわれる閻魔法王様と司命尊、司録尊、小野篁卿に参って欲しいものです。壁画は、現存する地獄壁画の板絵としては我が国最大のもので、桃山時代に狩野派によって描かれました。当時に書かれた宣教師ルイスフロイスの「日本史」にも登場しています。

早々に同寺の戸田妙昭庵主にお話を伺うと、「ゑんま堂として知られるこの寺の正式名称は引接寺(いんじょうじ)です。かつて、あの世とこの世の境界のこの場所で、あちらに旅立つ人に引導を渡す場所だったのですよ。ご本尊の閻魔様は人々を地獄に落とすのではなく、地獄に行かないように怖い顔でいさめてくださるんです」とのこと。

1200年も前から続く古刹なので、何代目かは到底分からないですが、妙昭庵主様が50年副住職を務めた後、先代のお父様から預かられて15年になるのだそう。続けて桜満開の境内を案内してくださいました。本堂北にひときわ目立つ枝ぶりの桜は、普賢象桜ではなく、庵主様命名の「桜のさくら」(ショウゲツ)、賑やかしのさくらと掛けたお茶目な訳がありました。

痴情を描き、うそ(創作)の物語を書いたとされ、閻魔法王に地獄行きを告げられそうになるところを陪席の小野篁に助けられたとの伝承から、紫式部供養塔(重要文化財)と紫式部像があります。その供養塔の前にある2種3本が普賢象桜です。庵主様によると、「花の中央に雌しべがあって、普賢菩薩様が乗る白い象の牙に似ているので、その名が付いた」といいます。

室町時代には、後小松天皇が足利義満にその美しさを伝え、義満も普賢象桜の美しさに心を奪われたといいます。さらに江戸時代には、散る時には椿のように花が丸ごと落下することから、斬首を思わせるため、京都所司代は、その様を囚人に見せて改心させたともいわれています。お気軽に立ち寄ってみてください!
千本ゑんま堂 引接寺はこちら↓