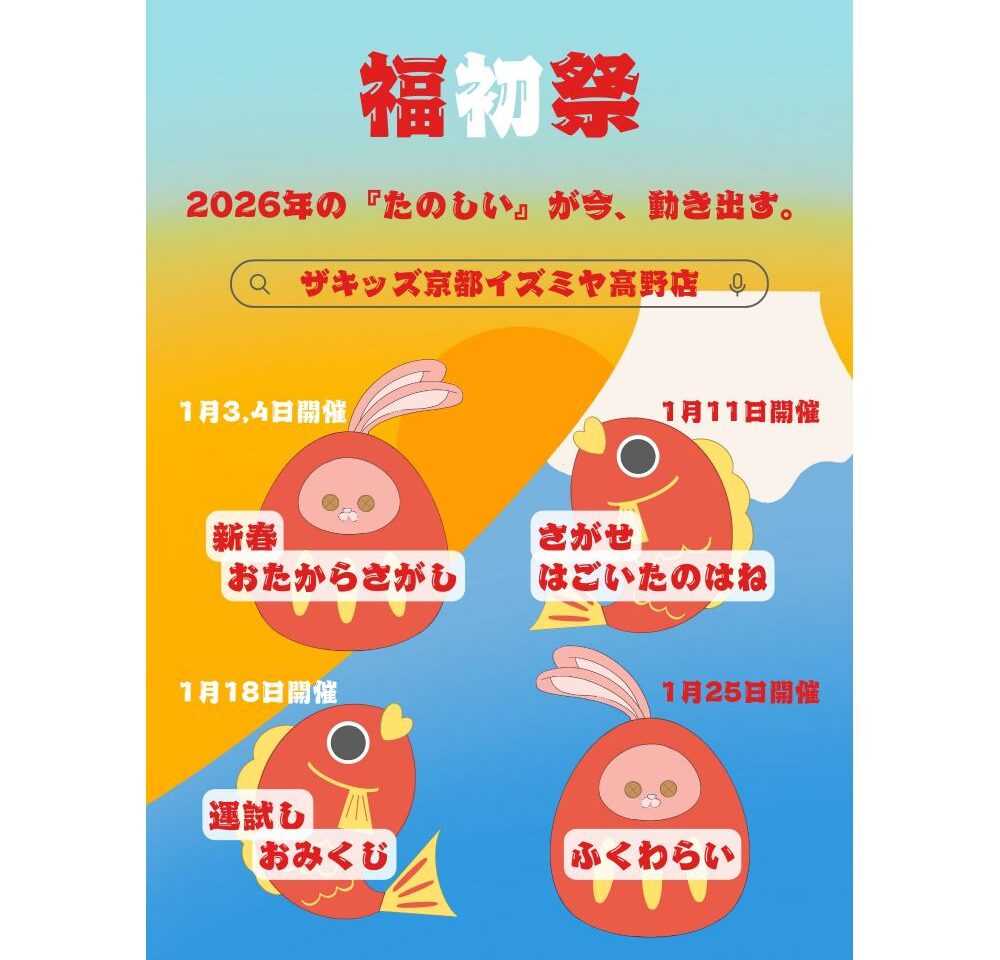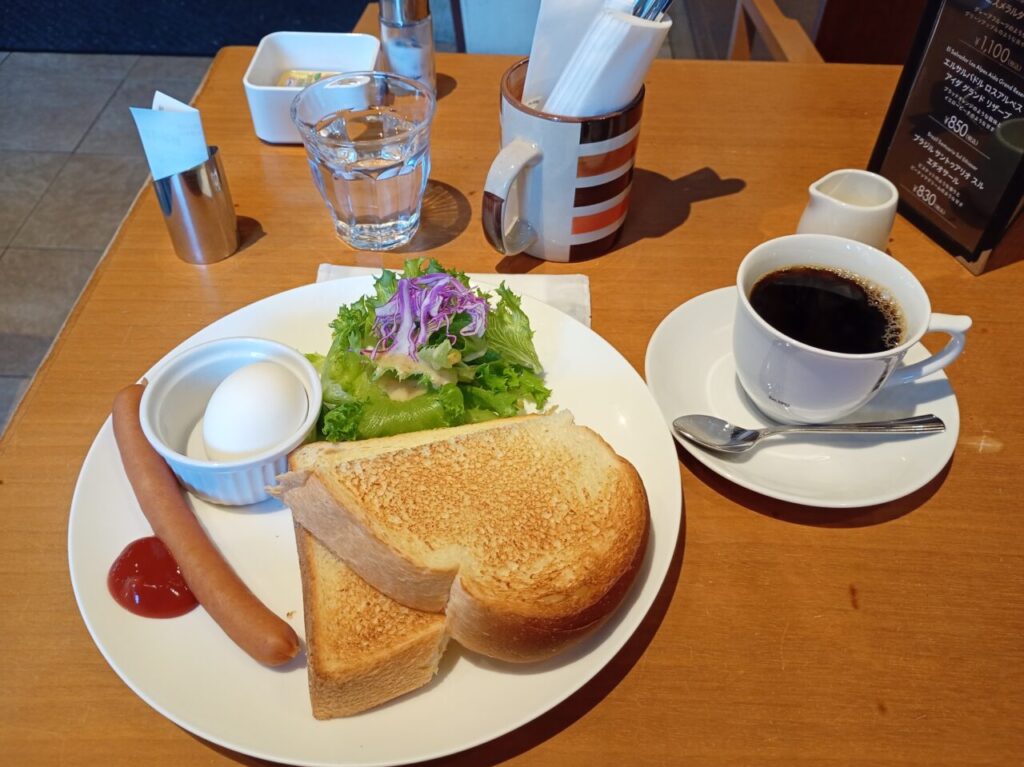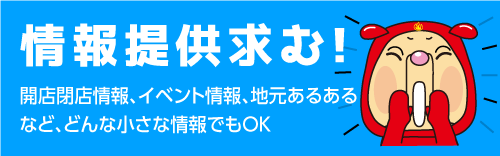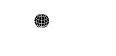【京都市西京区】淡く色づく紅葉が見ごろ! 600年続く名門武家「細川家」の歴史と一休禅師の母の愛が刻まれた「竹の寺」!
「皆様、ようこそ西京区へ。これからご案内するのは、都会の喧騒から離れ、静謐な歴史と自然の美しさを今に伝える名刹、地蔵院です。」と明るく優しい声。2025年11月28日、「西山山麓直感の旅 京都西山旅感」登録観光ガイドのまっすーさんに案内していただきました。

地蔵院は、通称「竹の寺」として知られる臨済禅宗の寺院です。皆様を包み込むこの清々しい竹の空間こそが、この寺の最大の魅力となっています。まっすーさんは、「さすがは竹の寺と呼ばれるだけあって、緑や竹林とのコントラストが素敵です」と、境内の景色を紹介します。紅葉はオレンジに近く淡く色づき、良い感じで見ごろを迎えていました。

🎋 細川家によって創建された竹の寺
地蔵院は、南北朝時代の貞治6年(1367年)に、室町幕府の最高権力者であった細川頼之によって、夢想礎石国師の高弟、宗鏡禅師を開山に迎え創建されました。頼之は、3代将軍・足利義満の若き日を支え、幕府の基盤を磐石にした名宰相です。創建の思いとして、頼之は禅の教えに深く帰依し、夢窓疎石の優れた高弟、宗鏡禅師を開山に招きました。この寺は、頼之が政務の疲れを癒し、禅の修行に励むための静かな祈りの場として大切にされました。

頼之の死後、地蔵院は細川家の菩提寺となりました。境内の一角には、頼之の墓所を示す「細川石」が今も静かにたたずんでいます。地蔵院は、細川家という武家の歴史と、禅宗の歴史が交差する重要な場所なのです。安産と延命のご利益のあるお地蔵様がご本尊です。
🎨 細川家当主と現代の芸術作品
地蔵院と細川家の繋がりは現代にも続いています。創建者・細川頼之公の末裔にあたる細川護熙元内閣総理大臣は、政治家を退いた後、陶芸や絵画などの創作活動に精力的に取り組まれています。

護熙氏は、先祖の創建したこの地蔵院の方丈に、自作の襖絵を奉納されました。これは、中国の有名な景勝地を描いた「瀟湘八景図」と伝えられています。600年以上前にこの寺を建てた細川家の精神と文化が、時を超えて現代の当主である元首相の芸術作品という形で今も残されているのは、非常に興味深い点です。

👶 一休禅師の母が隠棲した場所
「この寺の歴史を語る上で欠かせないのが、あの一休禅師とのゆかりです」と、まっすーさんは次のハイライトへと誘います。一休禅師の母は伊予の局という名で知られています。彼女は、当時北朝の天皇であった後小松天皇の寵愛を受け側室となりました。

懐妊した伊予の局は、天皇の后や周囲の者たちの嫉妬や陰謀に遭い、宮廷を追われることとなりました。彼女は、地蔵院の創建者である細川頼之公の奥方との縁を頼り、当時の細川家領地であったこの地蔵院の周辺で隠棲することになります。明徳5年(1394年)に、この地で一休宗純となる千菊丸を出産しました。境内には、幼い一休禅師を抱く母の姿をかたどった「一休禅師母子像」が建立されています。ここは、武家の権力闘争の中で生きた母の深い愛情を感じられる、静かなスポットです。

🌿 十六羅漢の庭園美
さあ、本堂へと進みましょう。地蔵院の方丈の前には、禅の教えを視覚化した美しい庭園が広がっています。
この平庭式枯山水庭園は「十六羅漢の庭」と呼ばれ、釈迦の教えを守る16人の弟子たち(羅漢)が修行する姿を表現しています。一面に敷き詰められた杉苔の深い緑と、その中に配置された16個の自然石。そして背景には、凛としてそびえる竹林の影。このコントラストが、見る者に深い静寂と安らぎを与えてくれます。まっすーさんは「心静かに座し、この清涼な空気を全身で感じてみてください」と、結びました。
衣笠山地蔵院はこちら↓