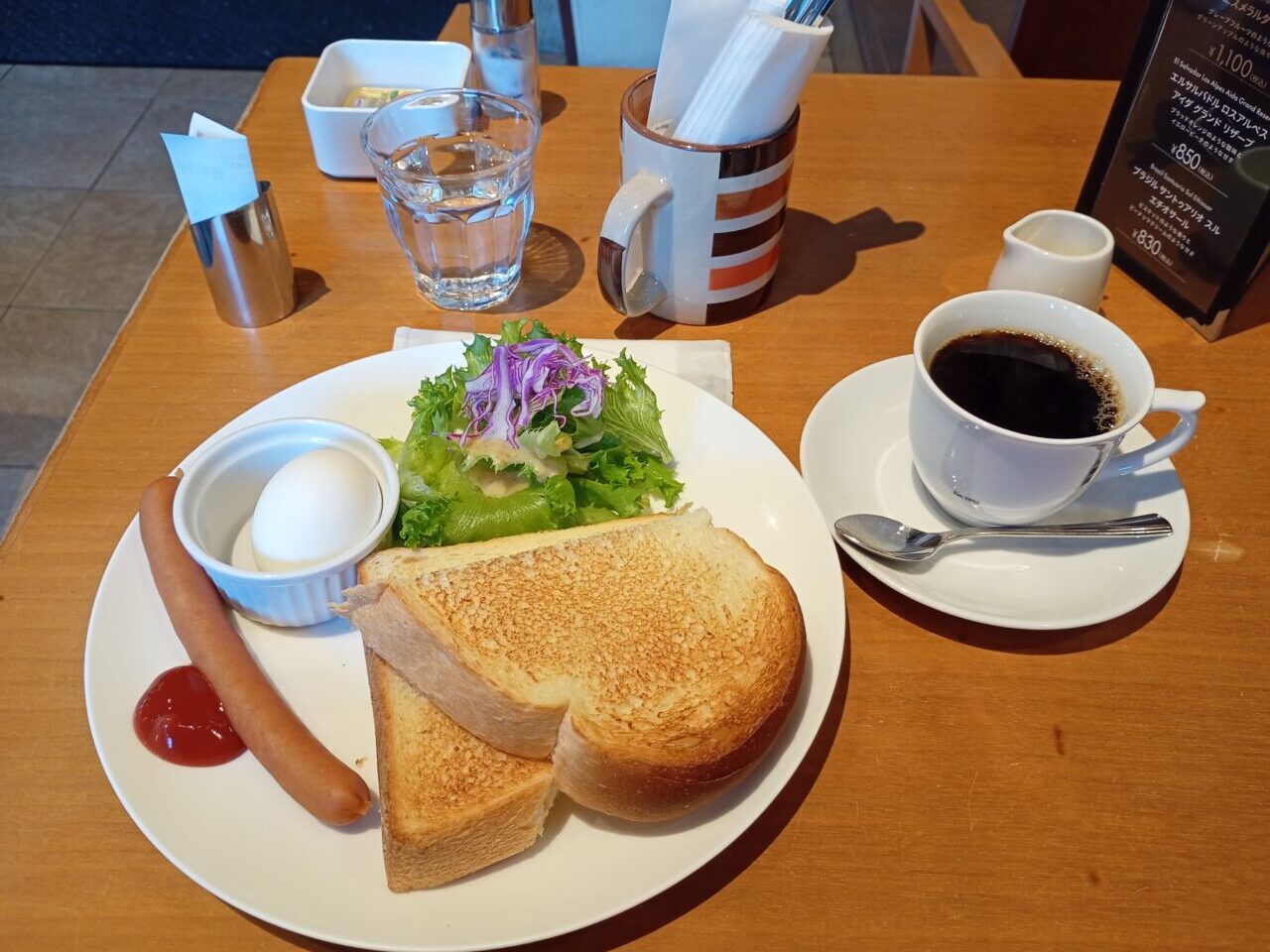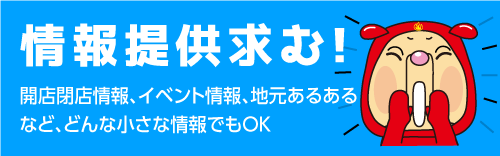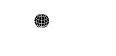【京都市西京区】将軍綱吉生母・桂昌院が復興させた善峯寺で歴史と「玉の輿」のご利益を学ぶ!
京都市西京区大原野にある善峯寺は、長元2年(1029年)に源算上人によって開かれました。山門を入ると、かつて応仁の乱で焼失するも、江戸時代中期に徳川五代将軍綱吉の生母である桂昌院の尽力で復興された伽藍が並びます。

復興の歴史と玉の輿のご利益
桂昌院は幼少期をこの地で過ごされ、篤く寺を信仰されました。その復興計画は多岐にわたり、綱吉公の42歳の厄年に際し寄進された「厄除けの鐘」や、桂昌院の家紋である「繋ぎ九つ目」紋が今も境内に残されています。

また、一般の平民から将軍の生母という異例の出世を遂げられた桂昌院にちなみ、薬師堂の出世薬師如来は「玉の輿」のご利益を授けるとして信仰を集めています。境内からの京都市街の眺望は、その出世を見守るかのようです。

秘められたご本尊とご利益
善峯寺のご本尊である千手観世音菩薩は、後朱雀天皇の勅命により洛東の鷲尾寺から遷座された由緒ある像です。西国三十三所巡礼の十九番札所のご本尊と兄弟にあたります。

さらに、かつて山頂に祀られていた釈迦如来の石仏は、病気平癒のご利益で知られてきましたが、阪神・淡路大震災での奇跡的な出来事から、現在は「入試合格」や「交通安全」のご利益も広がり、多くの参拝者が訪れます。この釈迦如来像は合掌した珍しいお姿で、手を合わせて触れることができる「なで仏」としても親しまれています。

境内には、樹齢600年を超える国指定天然記念物の遊龍の松や、創建当時の色彩に復元された多宝塔など、見どころが満載です。春の桜、初夏の紫陽花、秋の紅葉など、四季折々の美しい花を楽しめる「花の寺」善峯寺へ、ぜひ足をお運びください。
善峯寺はこちら↓