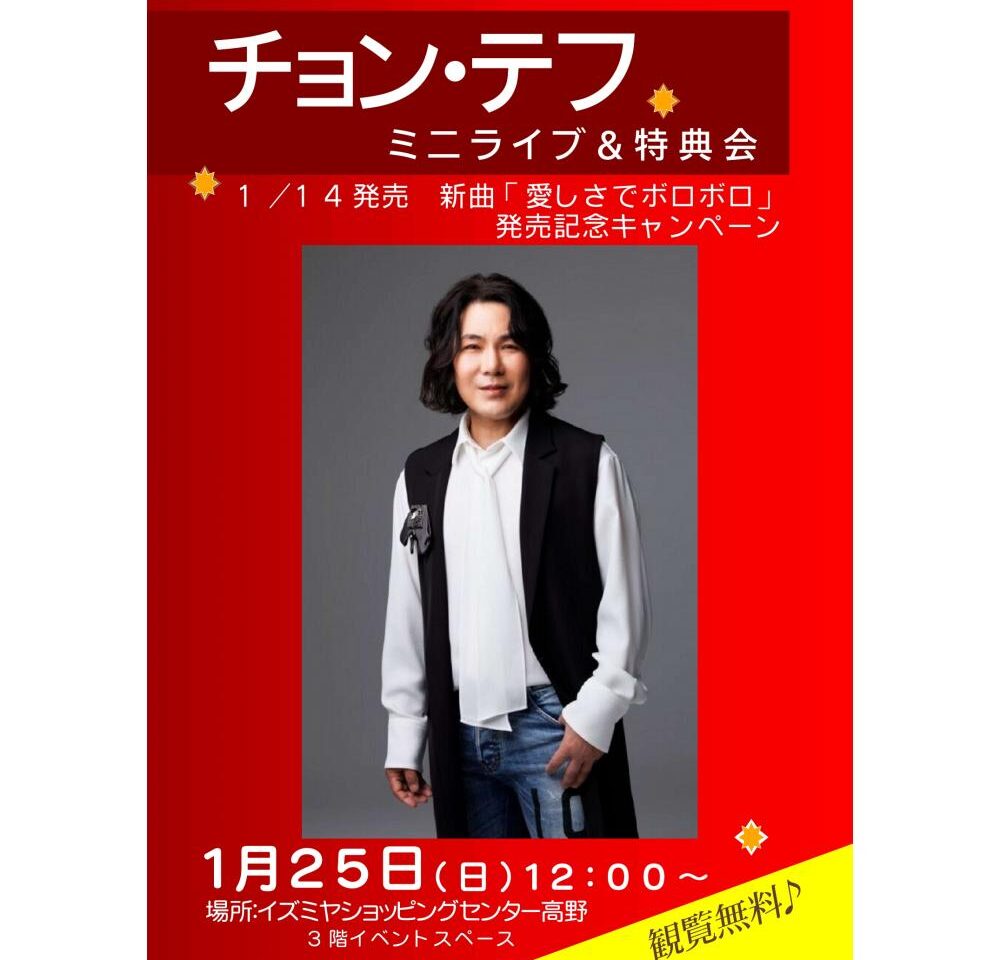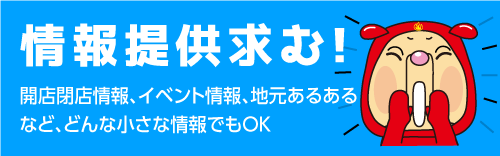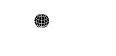【京都市伏見区】勝運と学問の神・藤森神社、深草の地に息づく1800年の歴史
深草の里に佇む藤森神社は、今から約1800年前に神功皇后によって創建された由緒ある古社です。平安遷都以前から地域の氏神として親しまれ、現在では勝運と馬の神社として全国から多くの参拝者が訪れています。2025年9月3日に訪れてみました。

日本書紀の編者・舎人親王を祀る学問の聖地
藤森神社の特色のひとつが、東殿に祀られている舎人親王(676-735年)の存在です。天武天皇の第六皇子である舎人親王は、日本最古の正史『日本書紀』の編修事業を総裁として指揮し、720年に完成させた学問の偉人です。学業成就や文学振興を願う人々にとって、まさに「学問の神」として深い信仰を集めています。
菖蒲の節句発祥の地として全国に知られる
藤森神社は菖蒲の節句発祥の神社として有名で、毎年5月5日に開催される「藤森祭」は京都の初夏を代表する祭りです。菖蒲が「尚武」に通じ、さらに「勝負」に繋がることから勝運の御利益があるとされ、競馬関係者をはじめ多くの人が必勝祈願に訪れます。祭りの見どころは勇壮な駈馬神事で、境内に設けられた馬場で繰り広げられる妙技は圧巻です。

初夏を彩る関西屈指の紫陽花名所
6月から7月にかけて境内の紫陽花苑が一般公開され、約3,500株の色とりどりの紫陽花が訪れる人々を魅了します。二つの苑に分かれた1,500坪の敷地では、期間中の土日に蹴鞠や雅楽の奉納行事も開催され、古典文化と花の美しさを同時に楽しむことができます。

皇室ゆかりの貴重な建造物
本殿は中御門天皇より下賜された御所の賢所で、現存する賢所建築としては最古のものです。境内には重要文化財の木造狛犬や紫絲威鎧も所蔵されており、歴史愛好家にとっても見逃せない文化財の宝庫となっています。

藤森神社はこちら↓