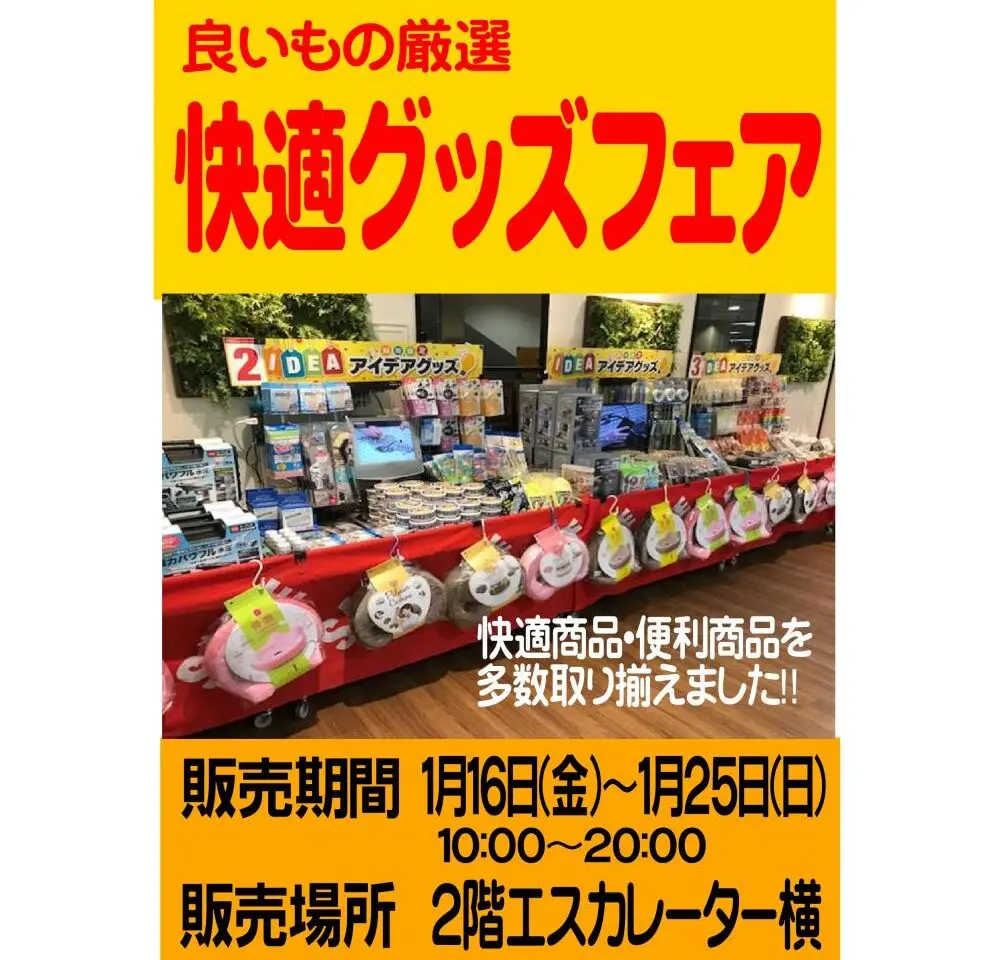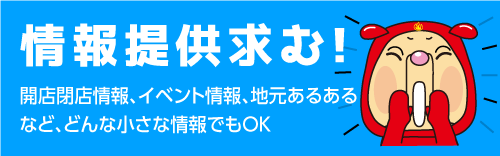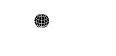【京都市伏見区】「かましきさん」で親しまれる勝念寺 織田信長から賜った仏像とチベット仏教の秘宝
京都市伏見区石屋町にある勝念寺は、地元で「かましきさん」の愛称で親しまれる歴史ある寺院です。丹波橋駅から徒歩わずか3分という立地の良さもあり、近年注目を集めています。天正15年(1587年)の開創以来、400年以上の歴史を誇る同寺。織田信長が深く帰依した聖誉貞安上人により建立され、本能寺の変後に正親町天皇の勅命で信長・信忠父子の菩提を弔うという重要な役割を担ってきました。

境内で最も注目すべきは、織田信長から直接賜ったとされる貴重な仏像群です。中でも釜敷地蔵尊は、地獄の釜茹の刑で苦しむ亡者の身代わりとなって苦痛を受ける慈悲深い地蔵様として、江戸時代から厚い信仰を集めています。

松葉俊明住職が特に興味深いと語るのが多羅観音(緑度母)です。「長年、由来不明の謎めいた仏像でしたが、最近の調査でチベット仏教の貴重な仏様と判明しました。専門家によれば、中国の元から明時代にかけて制作されたもので、チベット仏教の仏像としては国内最古級の可能性があります」と説明されています。

さらに平安時代末期、平清盛の時代に閻魔法王自身が彫ったとされる閻魔法王自作霊像も安置されており、その歴史的価値は計り知れません。寺院は「萩の寺」としても知られ、例年9月の彼岸頃には境内一面が美しい萩の花で彩られます。しかし松葉住職は「ここ数年の猛暑で開花パターンが変化しています」と環境変化への懸念を示します。それでも満開時の美しさは格別で、SNSでも話題となっています。

境内には身代わりの御利益にちなんで奉納されたユニークなカエルの置物も点在し、訪問者の心を和ませています。また、江戸時代の義民・柴屋伊兵衛の歴史的エピソードも残されており、伏見の地域史を物語る貴重な史跡でもあります。
小さな境内ながら、日本の歴史とチベット仏教文化が交差する稀有な空間として、文化財保護の観点からも注目される勝念寺。アクセスの良さと無料拝観という気軽さも相まって、歴史愛好家から地域住民まで幅広く親しまれています。
勝念寺はこちら↓