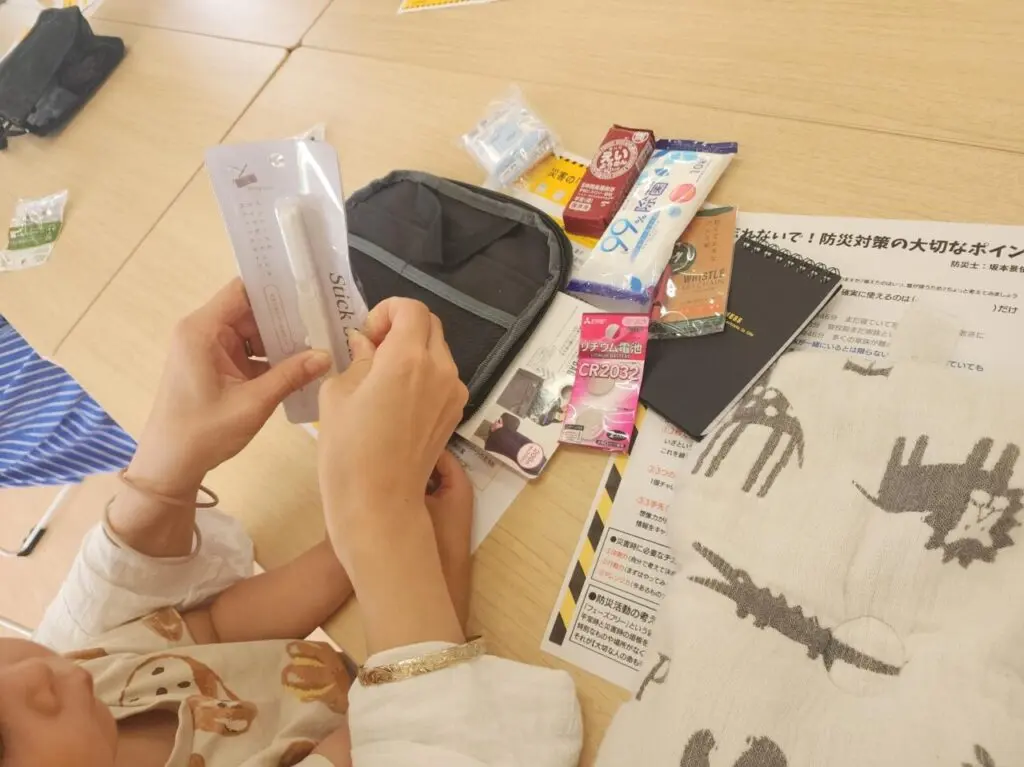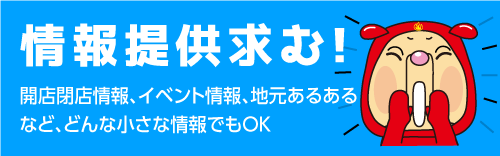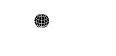【京都市右京区】映画の街太秦の昭和レトロな商店街周辺にある小さな3つの神社を巡ってみました!
太秦というところは彫刻としての国宝第1号となった弥勒菩薩半跏思惟像を有し、山城最古の寺院で渡来人の秦河勝が聖徳太子から仏像を賜り、建立したことから秦公寺とも呼ばれる広隆寺を中心に、秦氏の諸侯たちの古墳と推定される蛇塚古墳などの古墳群も点在する歴史ある街です。この周辺でも新緑が鮮やかになってきた2025年5月19日に、太秦周辺を歩いてみました。

大映通り商店街の真ん中に「映画神社」ともいわれる「三吉神社」が鎮座しています。昭和3年(1928年)に日活の撮影所が建設されることとなって、この場所にあった八丁藪という竹藪を切り開くと「三吉稲荷大明神」と「中里八幡大菩薩」の二つの小さな祠を発見しました。これらを一つにまとめて神社として創建したのが現在の社です。この日活の撮影所がのちに「大映京都撮影所」となりました。2001年には、日本映画の父と言われる牧野省三監督の顕彰碑が建立されました。また山田洋二監督や沢口靖子さんの直筆絵馬なども奉納されています。

太秦映画村の方へ歩いていると、広隆寺に隣接して大酒神社がありました。かつては広隆寺の桂宮院の境内に鎮守社として祀られていましたが、明治維新による神仏分離令によりこの場所へ移封されました。京都三大奇祭といわれる牛祭りの社としても知られます。御祭神は秦の始皇帝、弓月王、秦酒公です。「災難除け」「悪疫退散」のご利益があるといわれてます。

京都市の中心部へ戻る途中の三条通りで、車折神社の西、有栖川の近くで斎宮神社を見つけました。斎宮とは天皇の代替わりの際に伊勢神宮に奉仕した未婚の女性のことです。斎宮に選ばれた皇女は、神宮へ仕えるまでの間、心身を清めるため宮城内の潔斎所へ籠り、その後、外の浄地に野宮を設けて斎所とする決まりになっていました。この地は、その野宮の一つで有栖川禊(みそぎ)の旧跡とされています。また、伊勢神宮を創祀したといわれる垂仁天皇の第2皇女倭姫命の別荘地とも伝承されています。

さりげなく太古の歴史が隠されている太秦とはそんな土地柄なのかも知れませんね!
斎宮神社はこちら↓