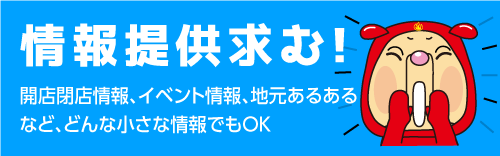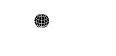【京都市西京区】藤原一族が招請した平安時代より続く社は、新緑輝く桂川周辺にひっそりと佇むんでいました!
ゴールデンウイークも明けて、日常の生活が始まった2025年5月8日に、桂大橋の周辺を訪れてみると、桂川沿いや桂離宮などが、まぶしいぐらいの新緑であふれていました。

西側に少し歩くと、春日神社がありました。こちらも境内が新緑に覆われていて、綺麗に輝いていました。創建年は不詳ですが、山背国葛野郡朝原村(現・桂学区)の氏神として、村民らの崇敬を集めてきたようです。藤原道長が造営した別荘である桂山荘は、現在の桂離宮の地にあったとされていますので、このあたりもその一部だったようです。

直ぐ近くに下桂御霊神社がありました。主祭神は、空海、嵯峨天皇と並んで本朝三筆の一人とされる能書家の橘逸勢(たちばなのはやなり) です。最澄や空海らとともに唐に渡った遣唐使の一員でありながら、学問は嫌いだったそうですが、書と琴を学び帰国。比叡山などの額にも用いられたほどの達筆だったそうです。従五位下・但馬権守の位にありましたが、藤原一族の他氏排斥事件といわれる「承和の変」により、伊豆に追放され、失脚しました。

橘逸勢が配流の途中に現在の静岡県で無念のうちに没した後に、都で天変地異など不幸が続いたため、それ以後に許され、八所御霊の一柱として御霊神社などに祀られ、鎮魂されました。下桂御霊神社の創建は、876年(貞観18年)と伝承されています。

境内には、樹齢400年のムクロジの樹があり、南参道の鳥居の扁額(へんがく)が独特の書体で面白い。これは後水尾天皇の宸筆(しんぴつ・天皇が自筆で書いた書物や文書)の写しで、現在のものは3代目になるのだそう。本物の初代の扁額は土蔵に収納されています。能舞台もあります。能舞台の廊下には、逸勢の書の一つ、伊都内親王願文(いとないしんのうがんもん)の写しが掲げられています。

下桂御霊神社はこちら↓